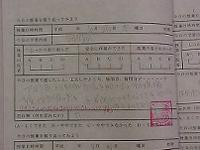学ぶ意欲を高める授業の工夫
−空き缶のリサイクルに着目して−
山梨県中巨摩郡竜王町立玉幡中学校 教諭 河西 修
Ⅰ はじめに
我国はめざましい経済成長を遂げ、豊かさを背景に生活様式や消費意識も変化してきた。しかしそれにともない、廃棄物の量は増大し、その最終処理場確保はますます困難となっている。ゴミ問題は緊迫した課題として私たちに提示されている。
米国では、飲料缶に占めるアルミ缶の割合はほぼ100%である。理由は、アルミ缶大手メーカーが積極的に技術開発と原価引下げに努めたことに加えて、アルミ缶のリサイクル特性に早くから注目したことにある。この例からわかるように、地球規模での環境保護が問題となり、未来への責任としてあらゆる分野でリサイクルが課題になっている。
生活に必要な技術の基礎基本の習得を目指す技術家庭科において、このような社会の現状について知り、アルミを初めとする金属の性質や加工法、そしてリサイクルについて考え学んでいくことは時代の要請に応える重要な課題だと考える。
今回は生活との密着度が高い金属を自らの目的に応じて再加工していく中で、金属の性質や加工に関する基礎基本を学び、生徒の個性の伸長をはかっていきたいという願いから、アルミ缶とスチール缶を金属加工領域で扱うことにした。特に、アルミ缶を材料として再生する過程では高温によりアルミが溶解していくという日常では経験しえない現象を目の当たりにする事ができる。この体験は純粋な感動と驚きを生みさらなる学習意欲の向上につながると考える。
生徒が自らの手によって空き缶を再利用する。過程での学習体験によって、地球環境の現状を捉え、一地球人として今後どのような態度が必要なのか、どのような知識や技術が必要なのかについて、生徒自身が自主的に判断し行動したなら素晴らしいことだろう。
Ⅱ 研究のねらい
本研究は、生徒の学ぶ意欲を高める授業を行うことをねらいとした。そのために下のような視点から研究を進めてきた。
1 リサイクルに関する意識調査
中巨摩郡下の中学校2・3年生357名を対象 とした実態調査を行い研究の基礎資料を得る。
2 題材の工夫
アルミ缶とスチール缶を生かした製作題材を検 討する。
3 授業計画の立案
アルミ缶とスチール缶のリサイクルを取り入れ た授業計画を立てる。
4 評価についての検討
学ぶ意欲を高める自己評価法を取り入れる。
Ⅲ 研究の内容
1 リサイクルに関する意識調査
平成10年4月に、中巨摩郡下の中学校2・3 年生357名を対象とした実態調査を行った。こ こでは質問項目をあげ結果は別紙参照とする。
Q1.リサイクル運動に関心はありますか。
Q2.リサイクル運動は必要だと思いますか。
Q3.リサイクル運動に参加した経験について教えて下さい。
Q4.家庭でのゴミの分別収集について教えて下さい。
Q5.リサイクル製品(再生品)の内、あなたはどんな物を使っていますか。
Q6.現在のスチール(鉄)缶のリサイクル率はどれくらいか知っていますか。
Q7.アルミ缶のリサイクル率はどれくらいか知っていますか。
Q8.リサイクルのための、空き缶拾いの経験について教えて下さい。
Q9.次のマークの意味または名称を知っている人は答えて下さい。
・リサイクルマーク ・エコマーク
Q10.回収された空き缶はどのような方法で処理されているか知っていますか。
Q11.回収した空き缶を利用して何かを作るとしたら、どんなことをしたいですか。
Q12.「リサイクル」について、あなたの感じていることを述べて下さい。
考察
スチール缶(リサイクル率=約80%)やアル ミ缶(リサイクル率=約70%)のリサイクル率 については、両者とも実際よりも少ない値を回答 しており、空き缶がそれほど回収されていないと 考えている実態がわかる。また、空き缶拾いの経 験については、一般のリサイクル運動と同様で、 ほとんど行ったことがない状況である。スチール 缶やアルミ缶リサイクルのマークについては、正 しく答えられた生徒は少数である。「エコマーク」 という答については、ほぼ半数の生徒が正しく回 答している。
回収された空き缶の処理方法については、ほとんどの生徒が「溶かして作り直す」と正しく回答をしている。
「回収した空き缶を利用して何かを作るとした ら、どんなことをしたいか」という問いに対しては、7割の生徒が「溶かして何かを作り直す」と 回答しており、金属の溶ける性質について関心を 持っていることが理解できる。
「リサイクルについて感じていることは」とい う問いに対しては、地球の資源とゴミ問題や再利 用と環境保全という立場で真面目に考えている様子が分かる。
アンケート調査より生徒のリサイクルに対する 関心度や必要性の高さを読み取ることができる。 しかし、その必要性を認めながらも、実際のリサイクル運動への参加やゴミの分別収集の実施状況 となるとあまり高くないと判断できる。それは中 学生にとってリサイクル運動を実際に行うことの 難しさが浮き彫りにされたといえる。しかし、加 工についての興味関心が高く、とりわけ溶解には 多くの期待感が含まれていると感じた。
2 題材の工夫
アルミ缶を溶かすことは意外に容易である。安 全に十分配慮する事を怠らなければ、設備は日常 生活品で間に合わせることもでき安価でもある。また、再生したアルミは磨いたり削ったりが比 較的容易であり、仕上がりも光沢があり魅力的な 作品を残すことができた。
特に与えられたものからの製作ではなく、すべての材料を自分で用意することで、製作に対する参加意識が高まったといえる。同時に、作品完成 までの意欲を非常に高めることとなった。
3 授業計画の立案
アルミ缶のリサイクルを取り入れた金属加工の 授業計画(選択)についても紙面の関係で省略す る。(別紙参照)
4 評価方法の工夫と実践
評価方法として、授業に対する取り組みの様子、 ペーパーテスト・実技テストのほか自己評価や相 互評価などを実施した。生徒の持つ資質、能力や 努力を的確に捉えるためには、より多くの情報を 基にして評価することが重要である。その中で本 支部では、特に自己評価に視点をあて、「生徒自 らが学習に対する責任を持ち、課題を解決しよう とする意欲」を引きだすための自己評価の方法に ついて取り組んだ。
今までは、授業の時間を確保し簡単に行えるチ
ェック法を中心としたものを多く取り入れてき た。これは、チェックする項目毎に1〜4段階の 選択肢から、自分の評価にもっとも近いものを選 ぶという方法であった。しかし、この方法では「生 徒自らが課題を解決していこうとする意欲」は十分に育ったとは言えず、更なる検討が必要となった。そこで、次の点を考慮して自己評価について検討した。
<学習者の立場より>
①学習に対する姿勢・自覚を高める。
②どこまでできたかわかったか、どんな課題を残
したか、次時の目標は何か明確にする。
<指導者の立場より>
①指導した内容が適切であったか確認する。
②生徒のつまずきに気づき、補足や助言を行う。
以上の検討をふまえ、「自ら文章で表現する方 法を中心として評価を毎時間行う。」「それに対す るアドバイスを行い次時の指導ポイントを考え授 業を展開する。」の2点を評価の中心とした。
この自己評価法を通して、「わからないことの 明確化」「わかった・できたという成就感」「どう してという新たな疑問」など、具体的なことにつ いて知ることができ、より生徒を理解した授業の 展開ができるようになった。
チェック表
Ⅳ 研究の成果
授業を終え生徒は次のような感想を残している。
「今回アルミ缶を再生利用した授業から普段何気なく使い捨てていたアルミ缶やスチール缶が重要な資源であることに気がつきました。ボーキサイトから作ると大きなエネルギーを使うこと。再生すればその約3%ほどのエネルギーで新品と変わらないアルミを再生することができることを知りました。でも、作業の時に使ったコンロの熱もすごかったのでリサイクルの重要性が身をもってわかりました。」
「自分でアルミの固まりを作ることからはじめることができたことには、自分でも感動しています。削ったり、磨いたりすることも大変楽しかったです。」「あんなにたくさんのアルミ缶が僕のペン立ての土台になりました。不思議だし、なによりこのペン立ては自分には価値があるように感じます。」
今回、身近な金属を利用して作品づくりを行った。ここで具体的なリサイクルを自分たちの手で行ったことは作品づくりの関心や意欲を高めるうえで非常に有効であったと思われる。作品づくりの過程ではスチール缶での製作をあわせ、ねじ切り、曲げ、切断、接合など基本的な作業要素も体験を通して学ぶことができた。また、自分たちが材料から製作したという誇りからか、満足げに見つめる生徒が非常に多かった。このことから判断しても生徒の学ぶ意欲を高める授業が展開できた。しかし、特に磨きには時間がかかり、作業効率と学習効率の改善が求められるので、製作題材には今後さらなる工夫が必要と考える。
実態調査から始まった今回の研究は、インターネットでの調べ学習や体験学習、自らの疑問に対する解決学習及び評価を経て、生徒の学ぶ意欲の向上、個性の伸長、技術教育の基礎基本の定着へ結びつくことができた。リサイクルへの取り組みは、今後更に領域、教科を越え総合的に展開していく必要があると思われる。
GO HOME