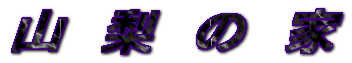
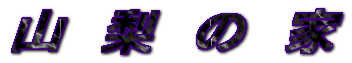
山 梨 の 家
参考文献 山梨の草葺民家 坂本高雄
用語解説 切妻造り 入母屋造り 入母屋の破風口 突き上げ屋根 甲屋根(カブト造り) 養蚕との関係
◆ 切妻(切妻造り・切破風造り)
切妻は屋根の両端を垂直に切り落した格好の単純な屋根である。
この屋根型の民家を山梨では切妻造りとか切破風造りと呼んでいる。
1732年の『甲州噺』に山梨県が諸国と異なって切つま切(切妻)であったこと、1814年の『甲斐国志』巻二には、切破風と呼んでいたことが記されている。
ハフには破風と博風があり、破風は風が通る穴であり、博風は風がよく当るところである。山梨の切妻が妻側によく窓を開けているところから切破風と呼ぶようになったというふうにいわれている。しかしはっきりしたことはわかっていない。
草葺の切妻造りはごく大まかにいうと県下全域に分布していた。甲府盆地東部を中心にした国中地方に多い。甲府盆地西部では北巨摩郡須王町江草仁田平、若神子と武川村を結んだ付近が北限で、南巨摩郡中富町と西八代郡下部町を結んだ付近が南限である。郡内地方では、笹子峠や御坂山地のいくつかの峠越えの旧交通路に沿ったところに、ごくわずか分布していた。
切妻造りは、古くから天地根元造りや屋形埴輪あるいは神社建築の様式に取り入れられてきている。山梨の切妻造りも天地根元造りが起源だとする人もいる。
切妻造りは全国的に見ると、ごく限られたところにしか分布していないし、その位置は内陸部にあって比較的風の弱いところである。屋根の基本型の中では、切妻が最も構造的に弱いといわれている。これらのことは自然条件と屋根型との強い関連性を示すものである。このことから国中地方、特に甲府盆地に切妻が多く分布する一因として気候の影響のあることが考えられる。
切妻は単純なかたちであるから、屋根を葺くのに比較的技巧を必要としない屋根である。そのために家を建てるのに経費が安上りに済むことにもなる。山梨は山間の地にあって生産力が低く、生活条件に恵まれてはいなかった。すまい造りには実益性が優先されたことが想像できる。こんな社会的要因も切妻の分布する理由のひとつであろう。
切妻の屋根を葺くのに技巧を必要としないと書いたが、実はけらばの箇所は例外である。草葺の場合、材料を流れの方向に葺くからそこはさばけてしまって止めようがない。そのため、けらばの箇所は斜めに小口を見せて葺いている。たいへん厄介な技術を必要とするところであるから、切妻が屋根葺技術の面から敬還される理由になっている。こうなると山梨の屋根葺技術はたいへん高度であるといえる。屋根の葺きかたも長い伝統的技術に支えられているとみてよいだろう。
何といっても山梨の切妻造りの最大の特徴は、妻と軸部が一体になっている構造にある。草葺の切妻の屋根は排水の関係から勾配を急にしなければならない。それが構造的弱さを助長するので、建物としてはたいへん不安定なものになる。そのために柱や束、梁や貫を入れて補強する必要がでてくる。県下の切妻造りの妻側はこの木組みが実に巧妙に組まれ形態も様々である。
◆入母屋造り 
入母屋は寄棟の上に切妻を重ねた感じの技巧的な構成の屋根である。
入母屋造りは県下全体を見渡すと、切妻造りの周辺全域に分布している。特に甲信国境を北限に旧韮崎町付近を南限とした峡北地方、西八代郡下部町を中心にその周辺の河内及び郡内地方の富士吉田市付近や東部に多い。櫓造りの多い甲府盆地東部では見ることがない。
切妻造りと同様に入母屋造りの分布することは極めて特異な点である。入母屋はいくつかの型に分けることができる上に、それぞれが地域色を形成している。県下の入母屋は三つの型に分けられる。
・破風の小さいもの
・破風の立所を妻に寄せて大きな構えとしたもの
・切妻の妻壁に庇を取り付けた態のもの
である。
峡北地方の入母屋造りは茅葺の重厚な感じのものが多い。切妻の北限に接する須玉町若神子及び武川村を結ぶラインより北側の須玉町、高根町、長坂町、大泉村、小淵沢町が分布の中心地域である。あまり広くない分布圏であるが、屋根の外観は地域内においても違いが明瞭である。小淵沢町から大泉村、長坂町及び高根町あたりにかけては、下り棟に比べて下り隅棟がとても長いのでずんぐり型になり、塩川上流の東北部の須玉町旧増富村付近の場合はそれが短いので背伸びした感じである。ほかに切妻の妻側におだれと呼ぷ庇を葺き下ろして大屋根と結合させた型もある。
山梨の入母屋造りには地域差があるけれど、一七世紀後期から末期(江戸中期)にかけて成立していたという。養蚕の発展が要因とするにはまだ早い時期である。従って養蚕との関連は、入母屋が換気や採光に優れている点が活用されたと見る方が妥当だと思われる。また入母屋の全国的分布を見ると内陸にあるという共通点から自然条件も無視できないだろう。郡内地方の東部は武蔵、相模地方につづく西部山麓地域に隣接しているので山梨とは早くから経済文化面での交流があった。例えば、明治の初期ころまでは上野原町の商圏にあった村落も多かった。生業の中心が養蚕業であったために、甲斐絹の原料である繭が峠越しに郡内地方に移入されていたのである。郡内地方東部の土地条件や生活条件は、この西部山麓地域とたいへんよく似ているので、その地方で考案された生活適応型の大きな破風口をもった入母屋が郡内地方にも伝わってしだいに普及するようになったのだと考える。
破風口

入母屋の破風口は最も目につき易く装飾の大きい部分である。従って地域ごと、村ごとあるいは家ごとに特色があって民家に美しさを添えている。
全国的な傾向からみると、県下の場合は種類が少なく意匠も極めて素朴である。ただ郡内地方には大きな破風口に反りを持たせた破風板を回わし、堅格子に繁く貫を配した木連格子を嵌め込むか、板を縦に張って、つまり羽目板貼りにして広い押縁を水平に打ち付けるかした美しい破風飾りが一般化している。前例は郡内地方東部の入母屋地域、後の例は富士吉田市などの富士山麓が分布の中心である。
郡内地方においては蚕を飼う場所としては屋上だけであるから採光、換気あるいは煙出し日がたいへん重要になる。さらに二層以上の多層構造であるから破風口は大きいほどよいことになる。もちろん破風口を大きくすることは、実用面からだけとはいえない。何といっても破風は目につくところであるから、美しく飾りたいと思うところである。それに入母屋は古くから見栄えのする建築様式であったから、その美観に憧れて伝統形式に倣ったということも考えられる。
屋根棟や屋根の平の一部を突き上げた造りの家の屋根を突き上げ屋根という。小屋裏を利用するためには換気や採光を充分に取るようにしなけれぱならないが、一般的には両破風から取り入れている櫓造りでは、大棟の中央部を突き上げることでより多くの換気や採光を取り入れる工夫がされている。屋根を突き上げると三角形の小屋裏は明かるくなり、作業空間は立体的に拡がるからとても使い易くなる。その上、この方法だと改造によって使用空間を拡げる場合も経済的負担が随分と少なくて済む。
山梨の養蚕との関係
山梨の養蚕業は既に江戸時代中期から行われており、大きな収入源となっていた。明治時代に入ってからは発展が飛躍的となっている。これは生糸の海外需要増大という背景のなかで県政も積極的な養蚕の奨励政策を掲げたこととか、他の農産物に比べて収利性の高かったことなどの結果である。例えば明治45年の養蚕飼育農家は県下農家総戸数の実に九二%である。大正期には第一次世界大戦後の好況に支えられて一層盛況となり、大正10年の全国における本県の養蚕業の地位は養蚕農家戸数で第10位、収繭量は第七位の規模となっている。これが昭和5年には養蚕農家60310戸、桑園面積24720ク夕−ル、昭和14年の収繭量は21485520kgとなりこの前後が空前の最盛期であった。第二次世界大戦中から戦後にかけては食糧難時代であったから、桑園はことごとく食糧作物に転換されたために桑園面積は最盛期の三分の一、収繭量は明治中期ころの程度まで転落している。しかし昭和23年ころからの生糸の高騰が農家の生産意欲を刺激して、再ぴ養蚕が盛大に行われるようになった。1974年ではかつての養蚕業の主産地が果樹に転換したため大きく衰退しているが、県全体でみると収繭量は全国で第四位であり、農家の販売所得に占める養蚕からの収入は第一位である。この生産量の増加や品質の向上は、飼育技術の進歩に負うところが多大である。飼育法だけをみても長い間において様々な改良が試みられてきた。
郷土における蚕の飼育法についての大まかな変遷をたどってみる。明治の初期ころまでは自然のままに放置して、無雑作に桑葉を与える古くから行われてきた方法によるもので、これを天然育と呼んでいる。やがて清冷育という方法に変わっている。清冷育はせいりょう飼とも呼ばれ、天然育と同意に考えられてもいるが、定期的に桑を与えたり、部屋の開放によって冷涼を取り入れる点が異なっている。明治10年代になると県の技術指導が積極化するようになる。例えば明治16年には温度育の実習のために、福島県へ数人の伝習生が派遣されている。温度育は、稚蚕が比較的高い温度に抵抗力のある性質を利用して密閉室で飼育する方法である。明治30年代になると、給桑法の改良が進められ条桑育が奨励されるようになる。条桑育は製糸家の反対もあってひところ行われなかったけれど、給桑回数は少なく人手が省けるし、廃桑は今までの三割近くも少なくて済むので、大正初期ころからしだいに普及するようになった。
天然育では常に温度が同じで乾燥していることが蚕育に有利である。小屋裏はこの条件を満すから山間部を中心によく利用されたし、天井は簀子張りにしたり、妻側に窓を取り付けて通気採光をよくすることも工夫された。温度育の稚蚕は密閉室で育てるから室は熱の拡散が少ないだけよいわけで、そのために天井を低くしで簀子を総板張りに替えるようになった。同じ温度育でも壮蚕の時期になると春蚕では保温と適当な湿度を、夏秋蚕では冷涼と湿度を取った飼いかたになる。成長の最も活発な時期であるから給桑量も多くなり、湿度も増してくるので通風換気が大切になる。そのために壁を少なくしたり、屋根に気抜けを設けることが考案され、採光についても夕日の直射を避けることが望ましいことから、家の向きは南面にするのがよいとされるようになった。居室の広さは六畳ないしは八畳が一般的であるけれど、条桑育が普及してからは一○畳の間取りが出現したが、これは給桑作業が最も能率的に行える広さであった。養蚕は屋内飼育が建前であるから養蚕技術の変化に呼応しながら様々な家の改造が行われてきた。